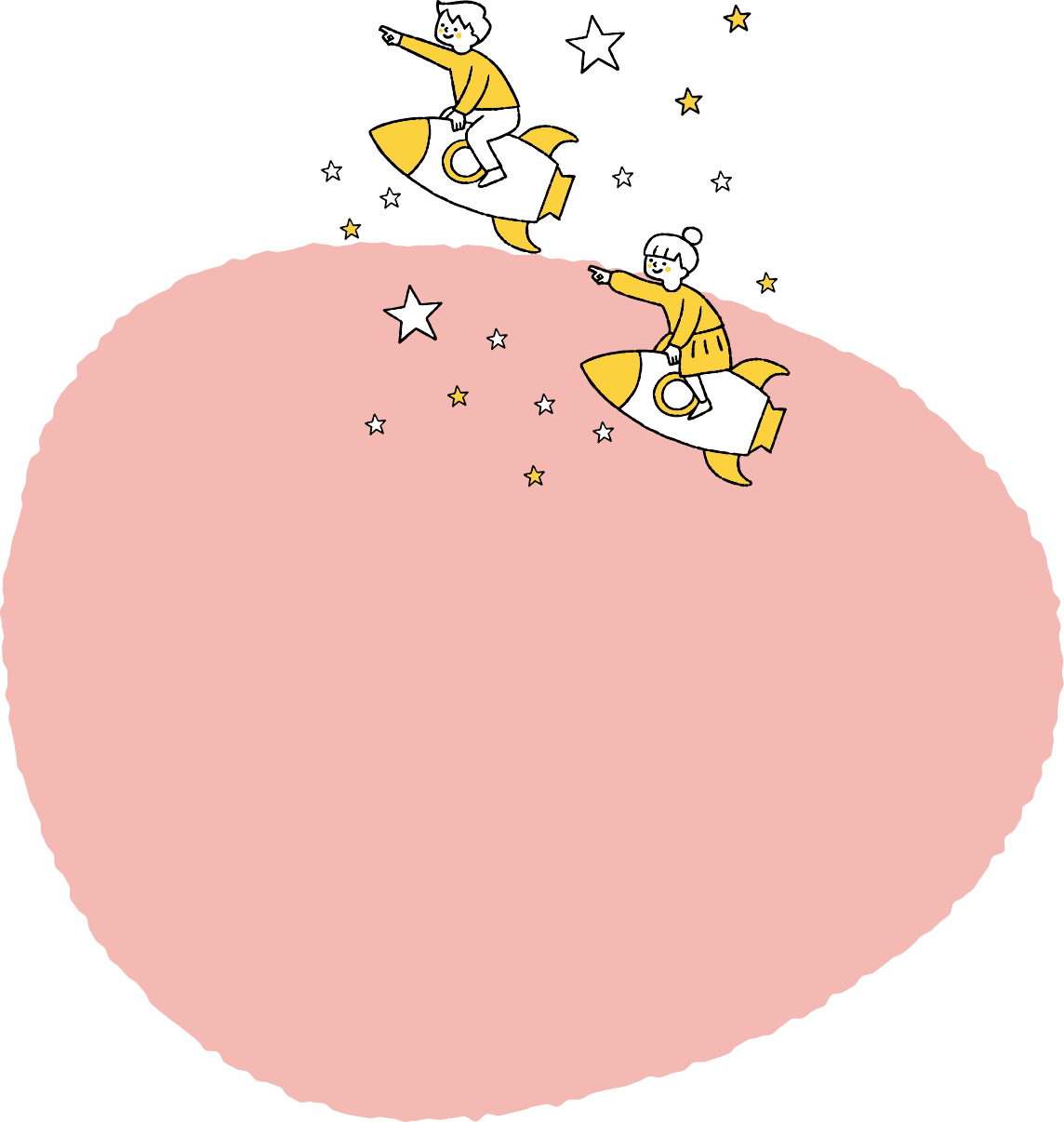環境が薬になる
人は地球という環境に生きています。天気が良ければ気分も晴れます。逆に天気が悪いと心も曇り、身体まで重たくなってきます。建物の中でずっと座って仕事ばかりしていれば、健康を害すことがあります。自然の中にでかけて適度な活動をすれば、心身共に健康になることができます。このように、人は取り巻く環境に心も体も影響される生き物なのです。そして、人は社会の中に生きています。周囲にいる人たちとの関係も「環境」の一部です。良い関わり合いが多いほうがいいに決まっています。
そのことに気づいてから、私は医療として薬剤のみで治療をすることの限界を感じ始めました。例えば、不安や気分の落ち込みであれば、良い環境に身を置くだけで、薬剤など使わずとも症状はよくなるかもしれない。身体の病気に対して薬剤を使うとしても、どんな場所でどんな医師から処方されたかによって効果も違ってくるでしょう。
であれば、そんな良い環境を創っていこう、自身が良い環境となるような医師を目指していこう、そう考えて始まったのがだいだいの丘プロジェクトです。
「環境が薬になる」の体現のために、カフェを併設したクリニックを中心としてプロジェクトは動き始めています。
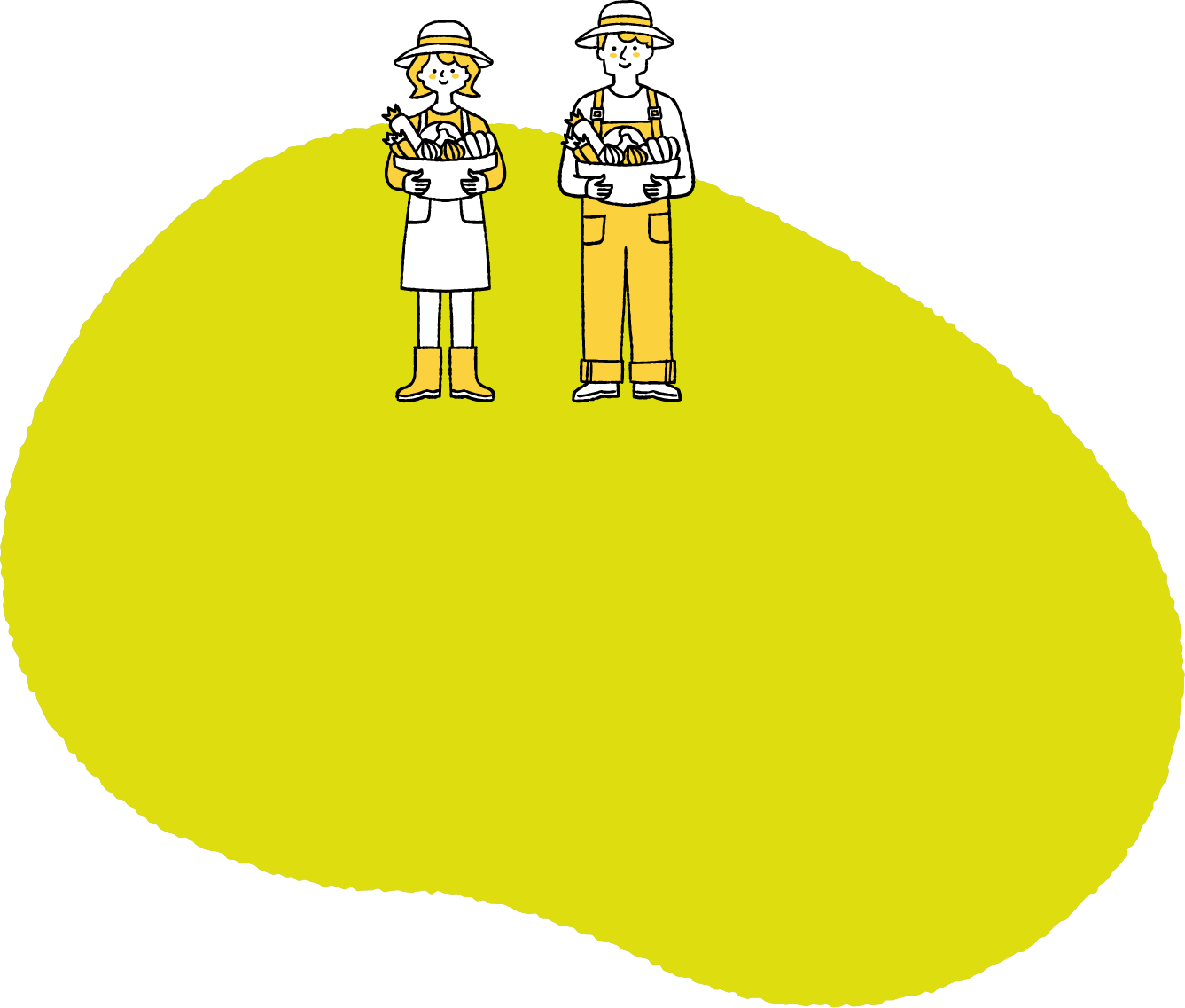
サードプレイス
サードプレイスとは、アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグがその重要性を説いた「第3の場所」のことです。
自宅(第1の場所)や学校、職場(第2の場所)も生きていくうえでなくてはならない場所ですが、一方で様々なルールやしがらみがあり、我満を強いられる場所でもあります。サードプレイスは第1/第2の場所とは異なり、自分をある程度解放できる心地のいい「居場所」のことで、第1/第2の場所で疲れている現代人にとって必要な場所です。どこがサードプレイスとなるかは人によって様々ですが、趣味の集まり、行きつけのカフェ、地域の理髪店・美容室などが例にあげられます。サードプレイスは、自分らしさを表せることで、ストレスを軽減する効果があり、人の生活に潤いを与えてくれます。また、飾らない自分のまま人と交流することで、孤立や疎外感を軽減する効果もあります。生きるため生活のためにある場所だけではなく、精神的余白としてのサードプレイスの存在は、疎遠化が進む現代社会でウェルビーイングを向上するためになくてはならない場所なのです。だいだいの丘プロジェクトは、これまで自然発生的にできていたサードプレイスを、意図して増やしていく取り組みです。
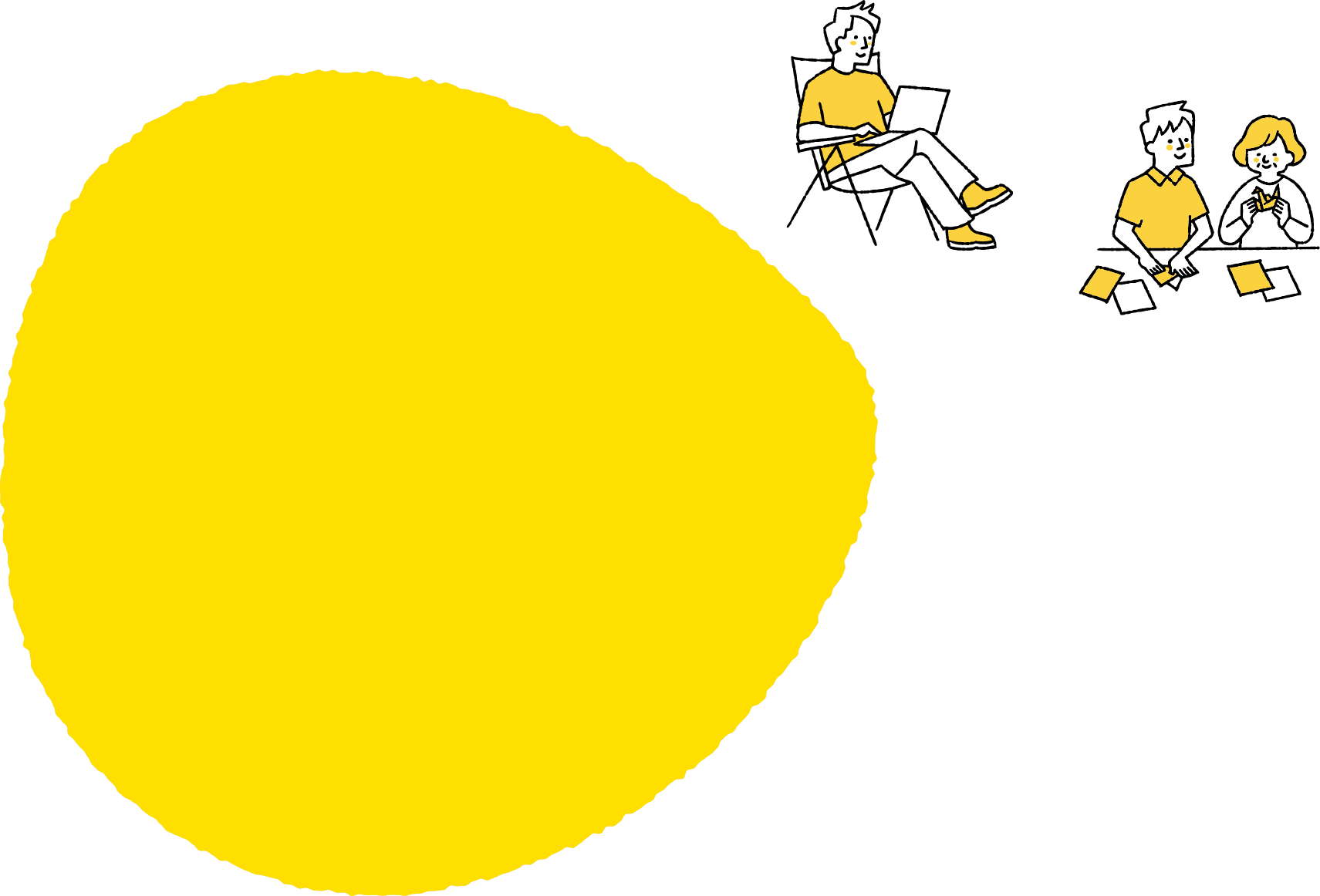
cafeだいだいの丘
だいだいの丘に立つ建物、半分はクリニックですが、もう半分はカフェになっています。クリニックの待合室とカフェの間に境い目はありません。憂鬱になりがちな診察の待ち時間を、カフェでゆったり過ごすことができます。この工夫も環境が薬になるという思いからです。もちろん、カフェだけの利用も可能となっています。
カフェの椅子にはこだわっています。椅子自体の工夫というよりも、居場所のバリエーションを広くしています。ファミレスのようなベンチタイプが心地よいという人がいます。テーブルを囲んで仲間と過ごすのが好きな人たちもいます。ふたりでカウンターに隣り合うことを求めている人がいます。ひとりでPCに向かって仕事や勉学に励む人もいます。窓に向かって「ぼっち」の時間を必要としている人がいます。どんな座り方もその人にとっての正解。それぞれの居場所を見つけに来てください。
クリニックの運営するカフェですから、ドリンク&フードにもこだわっています。医師が監修したビタミン+ポリフェノールたっぷりのオリジナルブレンドコーヒーをはじめとして、健康や栄養に配慮したメニューを豊富に取り揃えています。心地よい空間で食事をして、心も身体も健康!を目指しましょう。

ケア・カフェ®︎
ケア・カフェ®︎は、まったく新しいコンセプトで行われる、医療者、介護者、福祉者の集まりです。ケアに関わる人が、行きつけのカフェを訪れるように気軽に集っておしゃべりをし、顔の見える関係を作る取り組みです。ここでいう「ケア」というのは、医療・介護・福祉ですが、特に福祉者という造語には広い意味を込めています。いわゆる障がい福祉だけではなく、学校教育や保育、法律関係、企業人であっても社会貢献に携わっているなど、人への配慮を行うすべての人を指しています。
従来、このような人達は、各領域内で頑張ってはいても、なかなか繋がりを持つことはありませんでした。それぞれを管轄する行政部署の違い(いわゆる縦割りの構造)などから、良い連携ができているとは言い難いのが現状です。そこで、ケア・カフェ®︎では、医療・介護・福祉に関わる人たちがフラットな雰囲気の中、まずは「顔の見える関係を築くこと」自体を目標にしています。極端にいえば会話の質や、知識の確かさを追及していないのです。まず、異領域がつながる、そうすれば現場のケアが自動的によくなっていくであろう、それがケア・カフェ®︎のコンセプトです。
旭川で生まれ全国に広がったケア・カフェ®︎、本家のケア・カフェ®︎あさひかわは、今、場所を移してcafeだいだいの丘で毎月開かれています(第1金曜日19:00~)。ケアに関わる人の参加をお待ちしています。
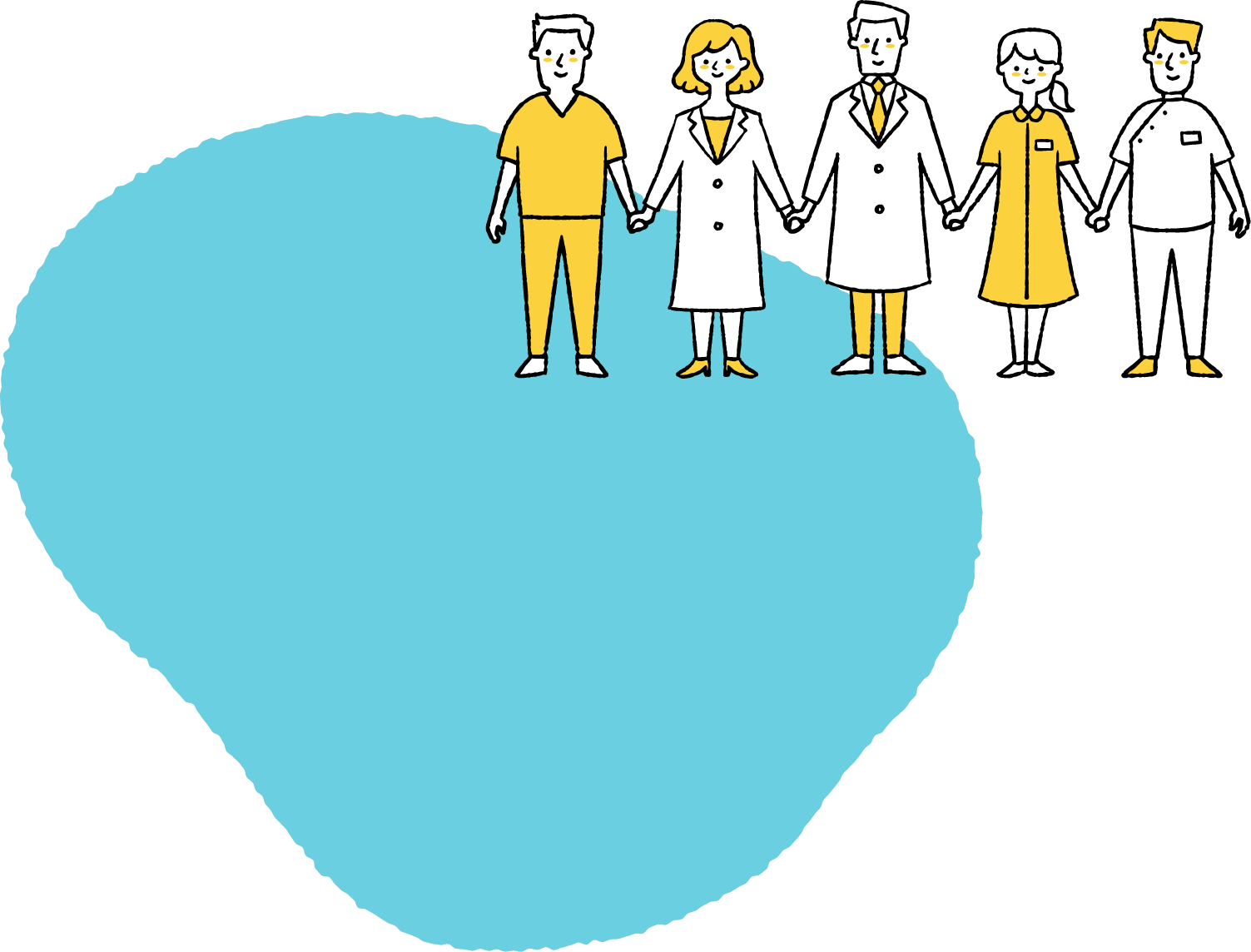
コミュニティの重層化
人は何かしらのコミュニティに属しています。町内会もコミュニティ、会社や学校、家庭だってコミュニティです。その他にも趣味の集まりや、スポーツクラブに属している人もいるでしょう。それもコミュニティです。でも今属しているコミュニティに居場所が見つけられなかったら?-とても生きづらくなることでしょう。心地よく安心できる居場所としてのコミュニティは誰にでも必要なのです。そのために、コミュニティを重層化していくことが大切だと考えています。
いくつものコミュニティに属していてもいいのです。その中から自分にぴったりあった(水が合う)コミュニティを見つけ出せばいい。また、似たような活動をしているコミュニティが複数あってもいいのです。活動が同じでも、コミュニティの居心地はまったく違うこともあります。いくつものコミュニティが同時並行して存在する、それをコミュニティの重層化と言っています。だいだいの丘には、既にいくつかのコミュニティが活動しています。ケア・カフェはもちろん、他にもいくつかのワークショップが開かれています。各種イベントも開かれています。ここでコミュニティが生まれ、コミュニティ同士が繋がって重層化していくところ、それがだいだいの丘という場所なんだと思っています。